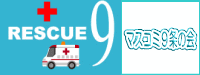コラム
![]()
宮下嶺夫(翻訳家)/図書紹介 「従属国―アメリカに抱きしめられた日本」/ 07/11/15
図書紹介
「従属国―アメリカに抱きしめられた日本」
宮下嶺夫(翻訳家)
この夏、Gavan McCormack著「Client State : Japan in the American Embrace」 (2007年6月Verso社刊、246頁。未邦訳) という本を読んだ。「従属国──アメリカに抱きしめられた日本」と訳していいだろう。ガバン・マコーマックはオーストラリア国立大学名誉教授でアジア・日本研究者。日本の大学でも教えており、「空虚な楽園──戦後日本の再検討」(みすず書房)、「北朝鮮をどう考える のか──冷戦のトラウマを越えて」(平凡社)など、邦訳されている著書も多い。
この「Client State 」は、1990年代から2007年初めまでの日本の政治状況の概観と分析である。著者によれば、この時期、特に2001年以後の小泉・安倍政権時代、日本は政治、経済、軍事など各分野で空前の変貌を遂げた。これは、基本的に、日本を、全地球的アメリカ帝国(the global US Empire)の中の一属国とし、自らの世界戦略に活用したいというアメリカの欲求が極度に高まったことによるものだ。
小泉の靖国参拝や、愛国心の注入と、権利よりも国家への義務の重視を目指す教育改革、戦時の日本国家の行為についての責任回避、日本独自の「美しさ」の強調、などに見られる民族主義的傾向の強まりも、アメリカへの従属の深化への過剰補償と見るべきだ。アメリカの抱擁(embrace)を脱して、アジア諸国との関係を改善し、日本国憲法の平和主義にもとづいて、ヨーロッパ同盟に匹敵する東アジア共同体の実現に向けて努力することこそ、今世紀の日本の進むべき道である、とマコーマックは言う。題名に含まれるembrace はジョン・ダワーのEmbracing Defeat(「敗北を抱きしめて」)にちなんだものである。
章立ては次の通り。
- 永遠の12歳? Forever Twelve Years Old?
- 従属的大国 The Dependent Superstate
- 日本モデルの解体 Dismantling the Japanese Model
- ブッシュ戦略の中の日本 Japan in Bush’s World
- アジアの中の日本 Japan in Asia
- 憲法と教育基本法 The constitution and the Fundamental Law of Education
- 沖縄──「処分」と抵抗 Okinawa: Disposal and Resistance
- 潜在的核保有国としての日本 Japan as a Nuclear State
- 分裂症的国家か? The Schizophrenic State?
著者は日本の新聞、雑誌、回想録、文学作品などを広く読み随所に的確な引用を行ないつつ自説を展開している。 叙述される事実のあれこれは、すでに知られていることが多いのだが、このように整理されて明確な形で示されると、この国の現状の凄まじさに、あらためて愕然とする。
小泉・安倍政権などブッシュ追随・新自由主義政策推進勢力を、理路整然と、呵責なく批判しており、読んでいて小気味いい。一方、日本の市民社会に向ける著者の視線は驚くほど信頼感に満ち、その平和主義・民主主義志向に強い期待を寄せている。全体として、優れた現代日本論であり、「九条の会」につどう人々へのエールでもある。
以下、拾い読み的にまとめてみた(一部、原文を引用したが、該当箇所の邦文は必ずしも原文と厳密に対応してはいない)──。
日本の属国化構想は、すでに第二次大戦中の1942年、国務省へのライシャワーの助言──「戦後の日本をアメリカの傀儡とし (Japan after the war should be turned into America’s puppet,) 天皇を満州国の溥儀のような存在にすべきだ」という──にも述べられていた。日本従属国論は、かつては左翼だけの主張だったが、今日では自国のラジカルな変貌に危機感を抱く保守派によっても主張されている。たとえば久間章生、後藤田正晴、榊原英資、森田実らがそれぞれ「日本は米国の一州だ」「属国だ」と述べている。(2-3頁)
2006年6月末小泉がエルビス・プレスリーの記念館でブッシュを前にして歌った「Love me tender」は、単なるおふざけではなく、彼の心からのラブ・ソング(a true and spontaneous love-song)であり合衆国大統領への愛と服従のメッセージ(a message from the heart of love and submission to the US president)であったと見るべきだ。 小泉はその一ヵ月半後、靖国神社に、近隣諸国の意志に逆らい、直前に明らかになった昭和天皇の「心」をも無視して参拝した。ここに見られる、対米従属と、その一方での日本的儀式へのこだわり、アジア軽視は、小泉政権の抱いている矛盾を完璧に表現していた。(4-5頁、192頁)
小泉は一般的にナショナリストと見られていたが、彼のナショナリズムは実体というよりもポーズだった。ほとんどすべてのことについてワシントンの言いなりになっていたがゆえに、強烈なナショナリスト的外見で変装するしかなかったのだ(Faithful to Washington on almost everything, he had to disguise himself with strong Japanese accents and postures.) 。(87頁)
第二次大戦後における天皇制の存続は、当時のアメリカ政府の周到な計算に基づく措置だった。天皇を中心とした、単一民族の、純粋な文化と優越性を持った、ユニークな国家という思想に日本人が固執している限り、日本は人類の普遍的価値を代表できず、近隣諸国の反発を招いてアジアの孤児にならざるを得ず、グローバル・システムにおいてアメリカに代わる極とはなり得ない。天皇制維持は、アメリカの世界におけるヘゲモニーを継続させるための黙示的保証だった(Retention of the emperor carried the implicit guarantee of continuing American hegemony)。(124頁、200頁)
森喜朗の「天皇を中心とする神の国」論や、安倍晋三の「美しい国へ」に見られる日本の独自性・優越性の強調は「他者」への反対、人種混合への軽蔑と表裏をなすものであり、不同意者を「非国民」として排除する可能性を含んでいる。こうした思想は、オーストリアのハイダーやフランスのルペンなど欧州極右の主張と同類であり、21世紀、アジア共同体の成立に向けて努力すべきときに大きな障碍となる。
この特異な国家観を、強き日本への郷愁、20世紀の侵略・戦争責任についての消極的態度、そして、今世紀になっても続く対米従属、いっそう強まるアメリカの「抱擁」への欝憤、が支えているのである(It is underpinned by nostalgia for a strong Japan, by reluctance to concede responsibility for colonialism, aggression, and criminality in the twentieth century, and by a latent resentment of continuing twenty-first-century national subordination, and of the tightening US ‘embrace’.)。(14頁、199頁)
ブッシュの対テロ戦争への全面支援の開始とともに日本国内でテロル的状況が広まっている。小泉訪朝を実現させた外務官僚宅に爆弾が仕掛けられる。公衆便所に戦争反対の落書きをした24歳の青年が44日間拘束されたあと14ヵ月の禁錮を言い渡される。共産党機関紙を配布した公務員が総勢200人のa special task forceによって尾行されビデオ撮影され、逮捕されて10万円の罰金を言い渡される。62歳の退職教師が国歌反対のビラをまいたかどで8ヵ月の禁錮を求刑され、20万円の罰金刑を受ける。
立川の自衛隊宿舎にイラク派兵反対のビラを入れた3人の活動家が75日にわたって拘束され家宅捜索され6ヵ月の投獄を求刑される(地裁では無罪、高裁では逆転有罪)。58歳の僧侶が共産党のビラをまいたために23日間拘束され10万円の罰金を求刑される(地裁で無罪)。小泉の靖国参拝に反対した元自民党幹事長加藤紘一の自宅が焼打ちに遭う・・・・。(20-28頁)
加藤紘一宅焼打ち事件について、同じ自民党の後輩政治家である小泉総理大臣も安倍官房長官も、10日間にわたり何のコメントも発表しなかった。──テロに対して沈黙を守ることはテロへの同意を表明するに等しいと言われているにもかかわらず。(27頁)
新自由主義「構造改革」のもと、格差は拡大し、貧困層は増大し、自殺者数は世界最大となった。2004年の自殺者は3万2000。アメリカの比率の倍である。実際、日本に滞在していると、駅の放送で列車遅延の理由として「jinshin jiko」という戦慄すべき言葉を頻繁に耳にしなければならなくなっている。(39-44頁)
小泉は、アジアを軽視するという19世紀のパラダイムを受け継いだ。19世紀、アジアは後進、非文明、植民地化と同義語だった。日本はそれゆえ、自国の非アジア性、欧州的、ないしは名誉欧州的ステータスを強調した。そして20世紀、日本は二つの異なった態度でアジアと向き合った。
世紀の前半は、アジア支配という「明白な天命」を持った「長兄」として。後半はアメリカに保護された「西側」国家として。どちらも近隣諸国からの疑念を買った。結果はアジアにおける孤立だった。隣人たちとの心理的隔たりが続く限り、小泉の日本はアメリカに抱擁されるしか選択の余地がなかった。抱擁はますます強まり、アジアとの和解と協力はますます困難になった。そうなるとアメリカの抱擁はさらに強まる。日本の「北朝鮮問題」が未解決である限り、また歴史問題とりわけ靖国をめぐる中国との距離が埋まらない限り、アメリカへの依存は深まるばかりなのである。(86頁)
金正日独裁体制を存続させている最大のファクターは、アメリカと日本の敵意であるともいえる(By a paradoxical feedback process, no factor has helped sustain the Pyongyang dictatorship as much as US and Japanese hostility.) 。金正日は両国の北朝鮮への憎悪、脅迫を指摘することで自分の体制を正当化している。同様に、アメリカが、アジアへの軍事支配、日本と韓国への基地設置、ミサイル防衛システムの販売、等を続けるうえで、北朝鮮の脅威ほど有用なファクターはない。ある引退外務官僚は、2006年7月の北朝鮮のミサイル発射を、まるでブッシュの命令で発射したかのようだ、それほどアメリカの利益にかなっている、と論評した。
アメリカが東アジア支配、ひいては世界支配を維持しようとする限り、金正日体制を存続させることはアメリカにとって有益なのである(Paradoxically, to the extent that the US wishes to maintain its East Asian-─and global─empire, it benefits from keeping Kim Jong Il in power.) 。(113頁、119-120頁)
北朝鮮は(少なくとも過去半世紀の間は)侵略戦争を起こしていない、民主的に選挙された政権を転覆していない、核兵器による脅迫を行なっていない、そして、無思慮な行為ではあるがミサイル発射や核実験はいかなる法律にも違反するものではない。確かに、北朝鮮は自国民の権利を踏みにじっている。しかし、2006年4月、ブッシュが、拉致された日本人少女の親を引見して感動的な説教を垂れたとき、──多くの国々の多くの市民がCIAによって拘束されて牢獄に入れられ法律の埒外に置かれ、拷問を受けていることに、思いをいたす人はいなかった。また、20世紀に、朝鮮で、大規模な拉致事件が日本によって引き起こされ、70年後になってもなお適切な解決がなされていないことを、想起した人もいなかった。(112-113頁)
21世紀の初頭、中曽根康弘は、現在日本は終戦以来最大の、いや明治維新以来の最大の危機にある、権利ばかりを強調する戦後教育が国を滅ぼしたと述べ、当時の官房長官安倍晋三は、社会にはびこる不道徳(親殺し、育児放棄、拝金主義)への処方箋として教育基本法の改訂を主張した。また、国会議員西村真悟は、教育基本法改訂のための集会で、基本法改訂の目的は「国のために死ぬ覚悟のある日本人を作り出すことである」と述べた。
1947年の教育基本法を攻撃する者たちは、さかんに教育勅語を称揚するが、これに対し、哲学者梅原猛は、教育勅語を日本の伝統に根ざしたものだという人々がいるが、それは違う、教育勅語は日本の伝統に根ざしているどころか、むしろ明治政府による日本の宗教と伝統への意図的な攻撃であった、教育勅語は、天皇のために死ねという思想を教え込むことによって国民に甚大な被害をもたらしたのだ、と述べている。(143-144頁)
国旗国歌法制定時の約束に背いて、日の丸掲揚、君が代斉唱が、教育現場をはじめとして猛烈な勢いで強制されつつある。東京都教育委員の一人は、国旗国歌に反対する者は癌である、悪の根は引き抜き絶滅しなければならないと述べた。学校での式典はビデオ撮影され、教師たちが口を開いて歌っているか、声の出し方はどうか(低いか、中くらいか、大声か)、までがチェックされるに至っている。(147-148頁)
日本は唯一の被爆国であり非核三原則を一応の国是としているが、首相時代の岸信介や官房副長官時代の安倍晋三を含め多くの政治家が、核兵器保有への願望を口にしている。核大国アメリカへの全面的屈従も、核兵器廃絶の大義とは矛盾している。
アメリカとの同盟を抱きしめることによって日本は核兵器と先制使用をも抱きしめている(By embracing an alliance with the US, Japan also embraces nuclear weapons and pre-emption.)。日本の「極東の英国」化が日米双方の欲求であることを考えれば、日本が核武装の強化、核の先制使用を目指す英国政府の方針を見習わないという保証はない。しかし、日本の市民社会の核廃絶への意思は強固であり、核をめぐる諸問題の帰趨は、現在進行中の核官僚機構と市民社会とのたたかい (the ongoing contest between Japan’s nuclear bureaucracy and its civil society)によって決せられるだろう。(175-177頁、189-190頁)
明治初年の琉球処分以来、沖縄は、日本政府による差別的政策の対象となり続けてきた。第二次大戦末期の本土防衛の「捨て石」としての沖縄地上戦はその最たるものだった。講和条約成立時の沖縄放棄は第二の琉球処分であり、米軍基地を置いたままの本土復帰(事実は膨大な金額による沖縄「購入」)は第三の処分だった。そして第四の処分といえる普天間基地移転問題に対し、沖縄住民は、10年来、不屈の抵抗を続けている。
小泉・安倍らが破棄し改訂しようとしている憲法は、沖縄県民が数十年にわたってその実現のためにたたかってきた理想を具象化したものだった(The constitution that Koizumi, Abe and others wanted to scrap and rewrite embodied ideals for which Okinawans had been struggling for a generation.)。それゆえ、普天間問題において、対立する二つの理念─沖縄の憲法擁護勢力と東京の憲法攻撃勢力─の間のたたかいは、これまでになく熾烈なものとなった(The contest between the two conflicting visions ─between Okinawan defenders of the constitution and its Tokyo attackers ─had never been sharper.)。
かつて琉球王国は軍隊よりも平和外交に依存した点で憲法九条を先取りした存在であった。この伝統を生かし、沖縄が、アメリカと日本政府のくびきを離れ、現在よりも自治の度合いを強めた反独立国的な地域となって、アジア諸国との懸け橋となり、日本本土の将来像のモデルになることが望まれる。(155-190頁)
改憲に関して、アメリカ製の1946年憲法に替えて日本人の手による憲法をつくるのだと主張されるが、自民党の憲法草案で見る限り、アメリカの利益と要望は、1946年憲法に劣らず反映されている。 近現代の憲法制定史のなかで、日本の改憲態度は非常にユニークなものである。一つは、外国政府の指示によりその利益のために行なわれている点。もう一つは、国家権力の拡大、個人の権利の縮小の意図を露骨に表現した文章が含まれている点だ。このような脅迫的文言は現代憲法史において前例がない(Modern constitutional history had no precedent for such threatening language.)。 憲法九条の改訂による自衛軍の設置を含め、改憲は、全体として、憲法上の義務として国民に愛国主義を押し付け、国家への尊敬と服従を要求し、さらに未来のアメリカ主導の軍事介入や戦争に日本が参加する蓋然性に道を開いている。(131頁、134頁)
一方、日本国民の平和主義は頑強である。戦後ほぼ一貫した九条改訂への政府の働きかけに対し、日本の市民社会は抵抗し、自らの憲法を誇らかに抱きしめ続けた(Japanese civil society resisted, tending to embrace its constitution proudly.)。安保闘争後の1960年から2001年までの18人の総理大臣は、就任の際、自分の任期中は改憲しないことを約束せざるを得なかった。
改憲の達成がまず不可能であり、もしあえてやろうとすれば政治的自殺になることを知っていたからである。世論調査において改憲そのものへの反対が減少した近年においても九条擁護の意見はなお大きな割合を占めている。自衛隊のイラク派遣に反対する意見も過半数を占めていたし、派遣後も、自衛隊が米軍の兵站支援を行なうことへの賛成意見は6パーセントにすぎなかった。
2004年に始まった憲法九条擁護を目的とした市民運動、「九条の会」は短時日のうちに急速に全国に広がった。憲法の精神に敵対する学者たちが編纂した新しい歴史・公民教科書は各地で反発を受け採択率は1パーセントに満たなかった。このような 地域レベルでの運動の表出は、民主主義・護憲主義勢力の根強さを示すものだった(these expressions of local initiative pointed to the continuing strength of democratic and constitutionalist forces.)。(127頁、137頁、139-140頁、146頁)
2004年4月、イラクで起きた若い日本人3人の人質事件は、右派とメディアと政府からの猛烈なバッシングを浴びた。しかし、彼らこそ、小泉がイラク派兵によって踏みにじった日本国憲法の原則を実現しようとした人々だった(it was they who had striven to put into practice the principles of the constitution──especially its rejection of the role of armed force in resolving international disputes──while Koizumi was actively subverting it. )。彼らは、占領軍の一部として武器を持って乗り込むのでなく、平和的に、自分たちの技能を生かして、イラクの民生に貢献しようとしたのである。彼らの行為こそ、日本の進むべき方向を指し示しているのでないだろうか。(71-72頁、203頁)
以上 このページのあたまにもどる
2007 archives
1)2007年6月26日米下院外交委員会で採択された「従軍慰安婦」問題に関する決議全文/(宮下嶺夫訳) /07/07/09
2)米国ワシントン・ポスト紙に掲載された日本人評論家、国会議員などによる従軍慰安婦問題に関する意見広告(宮下嶺夫訳) /07/07/09